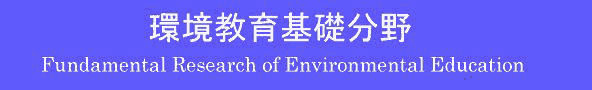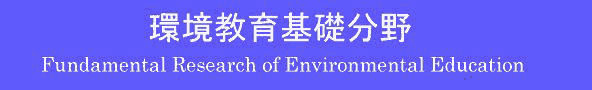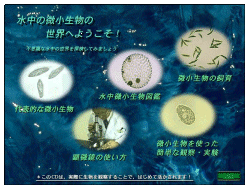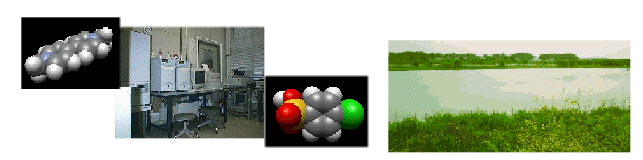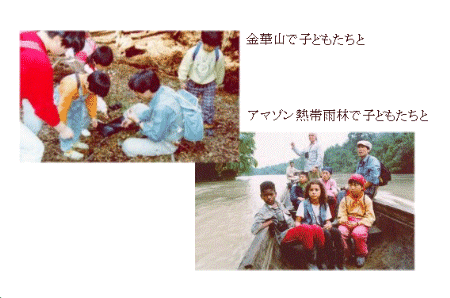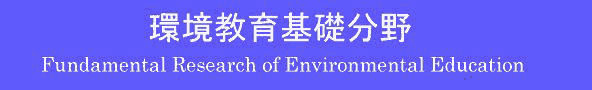
環境教育基礎分野では、学校教育における環境教育を推進するために必要な環境の各種事象と環境指標物質・生命などに関する総合的な認識を学習するための教材開発を目的としています。具体的には、生命科学の立場から、生命を育む自然、環境指標生物の役割と機能に関する研究、物質科学的立場から、環境指標物質の性質、動態、及び計測についての実験教材の開発研究、フィールドミュージアムに包含されるフィールドにおける環境基礎データの収集と教育利用、および環境教育教材データベースの構築とコンピュータグラフィックスによる環境教材の開発を行います。
|
[ 関連活動]
○実験観察法に関する研修会の定期的開催
○遺伝子実験室の管理・運用
○ガスクロマトグラフ質量分析計、イオンクロマト
グラフ、多項目迅速水質分析計、フーリエ変換赤外
分光光度計、BOD・COD測定装置の管理・運用
○ FT NMR, ESR装置(共同管理機器)の維持
|
|---|
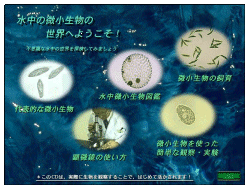
|
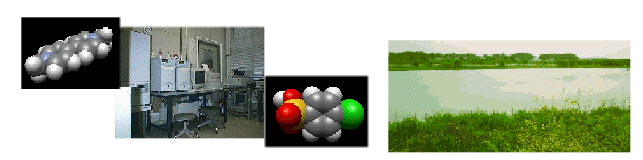

環境教育では、地球規模のさまざまな現代的環境問題を正しく認識するとともに、その認識を地域の自然や地域社会で具体的に実践することがきわめて重要です。そのためには、地域に密着した形での自然や文化の学際的研究を積み重ね、集積し、その成果を生きた環境教育教材として積極的に活用していく必要があるでしょう。
環境教育実践分野では、仙台市内や宮城県下にいくつかのフィールドを設定し、環境教育実践の場としてのフィールドミュージアムの実現をめざします。現在、牡鹿町・金華山の落葉広葉樹林や南米コロンビア・マカレナの熱帯雨林を対象に取り組んでいるスーパーネイチャリングセンター構想(SNC構想)に基づく諸活動もその一つです。
|
[ 関連活動]
○フィールドでの動植物の生態調査○調査成果公表のための雑誌発行
○各種自然観察会の企画と実践
○自然観察会の実践報告書の発行
○全学に開かれたフィールドワーク合同研究室の設置と運営
○フィールドワーク談話会(公開)の定期的開催
○環境教育に関わる諸機関・団体等とのネットワーク作り
|
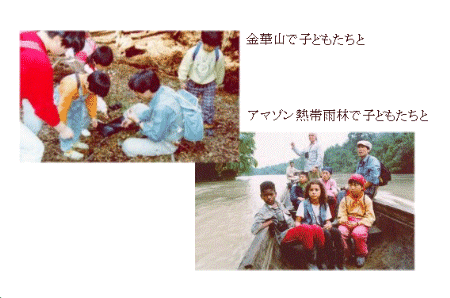
|
|---|