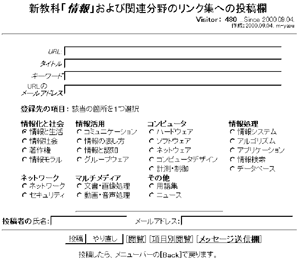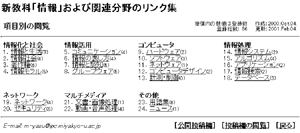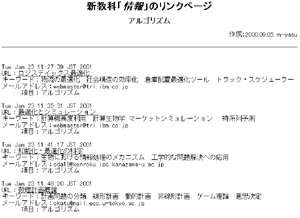研究報告
環境と情報教育の支援をめざしたリンク集生成ツールの開発
安江正治*
要旨:インターネット上に公開されている情報資源を学校教育現場からも利用しやすくできる機能を備えた利用者参加型のリンク集生成ツールを開発した。環境教育や情報教育などの分野についてリンク集を教師が共同で生成し運用するためのソフトウェアで、初心者にも簡単に使える特徴を備えている。
キーワード:リンク集生成ツール、オンライン登録、共同作業、閲覧メニュー、投稿欄 |
1.はじめに
教育分野の関係者にとって、この2001年は変革の年である。本学が所属する組織は旧来の文部省から、科学技術庁を統合した文部科学省(Ministry of Education,Culture, Sports, Science and Technology)と改組され、これからは、教育界をとりまく状況も変化してくることが予想される。文部科学省の英文名称に、TECHNOLOGYが使われており、教育分野においても、教師は技術といかに関わるかが問われてくることになると思われる。
現代社会は技術革新によって、物とエネルギーと情報のうごきが以前と比べて格段にはやくなり、人々の生活にも大きな影響を及ぼしている。そのような技術革新の中で特筆できるのが情報分野の技術の変革の速さである。現在、机の上の小さなコンピュータは、思考のための道具の一つとなり、人々が遠隔地の仲間と協調して仕事を進めるのに使われている。
このような仕事のスタイルが、教育の場にも導入されようとしている。しかし、安易な情報技術の導入に対して、一種の危惧の意見もある。例えば、初等教育の現場において、まだ理解度の充分でない子どもたちが、インターネットの情報の世界に無防備のまま触れることへの対処の難しさが指摘されている。情報通信の有用さを仕事の上で必要としている専門家や社会の人たちと、学校教育の場においてまだ社会的に自立していない子どもたちを指導している教師との間で、情報技術に対する必要度に違いがあるのが現実である。このギャップを埋め、情報技術への理解を深め、必要に応じて、教育の場に活用できることが学校教育において望まれている。そのための方策の一つとして、インターネット上のコンテンツを教師たちが簡単に編集して、子どもたちの学習指導に活用するためのリンク集生成ツールを開発したので、その概要を報告する。
2.インターネット上のコンテンツのデータベース化の必要性
現在、Webコンテンツを管理しているWebサーバの総数は1千万台を越えており(文献1参照)、インターネット上に公開されているコンテンツは膨大な量になる。この大量の情報の中から、必要な資料を取りだすのは、それなりの経験と情報の中味を評価できる判断力とがいる。現在、必要な情報を取りだす方法として、ディレクトリサービスと検索サービスとがある。それぞれのサービスを行っているものとして
| ・ディレクトリサービス |
| |
Yahoo! JAPAN、Yahoo! きっず |
| ・検索サービス |
| |
Google、goo、infoseek |
などが知られている。しかし、これらのサービスを使っても、必要とするコンテンツを見つけるには熟練がいる。情報検索の仕方を修得するのは、一人で行うよりも、仲間の教師たちが共同して行えることが望ましい。教師たちからは、授業の単元や関連項目別に、参考になる資料を閲覧できるように教育情報のデータベースを整備しつつ、情報検索の手法と内容の識別力とを修得したいとの要望も寄せられている。教師たちのそのような共同作業を支援する目的で、一種のデータベース管理ソフトウェアを開発した。
3.ソフトウェアの仕様と構成
以下、このソフトウェアの機能説明と、その特徴、構成、および評価である。
機能:
| ・ |
構成は投稿欄、閲覧画面、メッセージ送信欄の3部構成 |
| ・ |
ユーザインターフェースは、ホームページの画面形式 |
| ・ |
投稿欄は、リンク集を生成するための登録画面で、リンク集に登録する内容を投稿形式で入力する。登録する項目の詳細説明は補足1にある。 |
特徴:
| ・ |
リンク集データベースのための登録は、ホームページの投稿欄の形式
登録画面の例は、図1参照 |
| ・ |
閲覧画面は、メニュー形式。
時系列(登録した時間順)形式と、項目別形式 (図2参照)とからなる。
後者には、各項目に登録されている数と登録総数を数値で明示している。
図2の各項目に対応する画面は、図1の登録画面から、自動的に更新される。 |
| ・ |
メッセージ送信欄は、データベースの運用に関わる意見、例えば登録する項目の追加や修正等についての要望や意見を管理者に送るためのものである。
閲覧者は、電子メールを使うのではなく、入力画面からメッセージを入れるだけで、管理者にメッセージを送ることができる。 |
プログラム構成:
リンク集データベースは登録管理の部分と閲覧部分からなる。構成の概念は表1の通り。括弧内は処理プログラム名を示す。
プログラム名の拡張子html,pl,awkは、それぞれ使用した言語を表す。htmlはハイパーテキストマークアップ(hyper Text Markup language)言語でホームページの記述に使われている。(文献2参照)
plはperl言語、awkはシェルスクリプト言語の意味。
表1の項目別登録数の分析のプログラムリストは、補足2に示す。
評価:
研究プロジェクトが、多くの分野からできている場合、各研究者が各自の研究成果をインターネット上に公開できる形で電子化し、それらの内容を統合し、検索、閲覧しやすい形で、データベース化することがよく行われている。学校教育における情報や環境の学習においても、学習内容が多くの教科にかかわる場合、それぞれの教科の内容を各教科の担当者に分かる形に公開することが望ましい。この要望は、ネットワークの機能とここで開発したリンク集データ登録/閲覧プログラムで実現可能になる。
図1に示されている登録の項目は、高校の新教科「情報」(文献3参照)で取りあげられている内容を参考に、開発したソフトウェアの機能をテストするために設けたものであり、追加、修正等は簡単にできる。
これらの項目に関連したインターネット上のホームページの登録をオンライン化し、それぞれの項目の内容を簡便に閲覧できることは、既存のソフトウェアにはない特徴である。登録の際の項目として組み込んだ、キーワードも第3者が該当ページを検索したり、閲覧する際の手助けになるものである。図1の投稿欄には、「メッセージ送信欄」が設けられており、データベースの運用に関する意見を管理者宛に送ることができるようになっている。この機能は、データベースを利用者参加型の形で構築してゆくためには必須の機能である。
図2に示した項目別のメニュー画面から、登録された内容を簡単に閲覧できる。各項目に登録されているリンク先の数は、その項目の関心の大きさを表す目安になっている。図2の各項目に対応するリンク集の画面の例を図3に示す。
図1、2から分かるように、画面構成はホームページ形式の標準的なものであり、子どもたちにも使いやすい構成になっている。図1で入力する投稿者の氏名とメールアドレスは、個人情報の性格を有するので、この部分は管理者が閲覧する管理ファイルにのみ格納するようにし、公開を目的とする図3の画面には表示しない配慮を施した。
また、このソフトウェアは、本学の情報処理センターのファイルサーバ上で運用している。使用した言語はシェルスクリプトであったが、他のサイトへの移植に適した、より汎用性の高いPerl言語による記述に変更した。この改良により、各地域の教育機関が管理するコンピュータシステムにも導入しやすくなったといえる。
最近、教材データベースは、ビデオ画像を取り入れ、よりリアルな事例をホームページを介して伝えることができるようになってきている。本データベースは、そのようなビデオ画像のデータも参照することが可能であり、ネットワーク上に公開される教育教材データベースとして、教育分野への活用が期待されている。
| 表1 利用者参加型リンク集データベースプログラムの構成概念 |
--------------------------------------------------------------
登録ページ(online.html)
・アクセスカウンタ(count-on.pl)
・登録データの処理(regist-on.pl)
・項目別の登録数の分析(chk-url, add2.awk)
・メッセージ送信欄(mailto.html)
閲覧ページ
・項目別 (main.html)
項目メニュー --- 項目別閲覧({L1-L24}.html)
|------ 投稿欄/投稿の閲覧
(netregist.html, net-regist-on.pl, agenda.html)
・時系列順(list.html)
管理用の時系列データ(1行/登録)(raw.html)
--------------------------------------------------------------
|
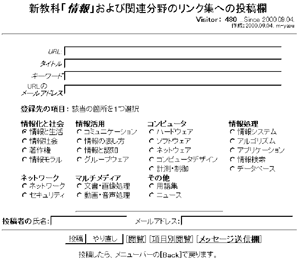 |
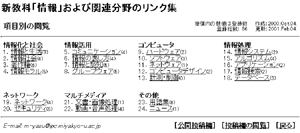 |
| 図1 リンク集生成のための投稿欄の例 |
図2 図1の画面から生成された項目別リンク集の主画面 |
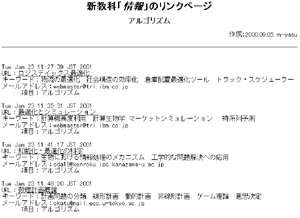 |
図3 項目別リンク集の画面の例。
図2の項目15「アルゴリズム」を選択すると呼び出される画面 |
3.まとめ
この報告では、データベース管理ソフトウェア開発の対象とする領域として、情報教育の分野を取りあげているが、環境教育の分野にも応用が可能である。また、インターネットの世界の情報は、相互に協力し合って、知識を互いに共有し合うことが基本にあり、この精神を学校教育にかかわる教師にもこのソフトウェアの活用を通して理解してもらいたいことが、この開発の動機でもあった。
開発されたソフトウェアは、図1の説明にあるアドレス(URL,Universal Resource Locator)で公開されている。このリンク集を共同作業的に構築できることを、本学の環境教育実践専修の大学院の授業等で検証し、登録内容を互いに確認し合うことで、新しい項目の追加の必要性に気づいたり、適切でないリンク先の削除など、教育情報のデータベースとして性格付けを行うことができることが検証された。
環境情報データベースは、利用者が自分たちの観察し体験した内容を構築できる機能を備えているべきである。この意味で、利用者参加型のデータベースは、教育分野から強く求められてきている。今回開発したソフトウェアは、その期待に応えるべく、環境教育教材として有用なホームページのリンク集を投稿形式で自動生成する機能を備えている。今後、環境教育教材に関心のあるグループと共に、この環境教育分野のリンク集の整備に応用する計画である。
参考文献:
1)The Netcraft Web Server Survey
2)高田敏弘、World-Wide Web
3)情報処理学会 情報処理教育委員会 初等中等情報教育委員会 高等学校 普通教科『情報』の試作教科書
補足1.リンク集登録画面の項目説明
- URL:相手先のホームページアドレス(URLはUniversal Resource Locator)
URLの解説は文献2参照。
- タイトル:相手先のホームページのタイトル
タイトルは、その内容を表す第一のキーワードである。
- キーワード:その内容を表すキーワードを複数入力できる。
キーワードの区切りは空白。
- URLのメールアドレス:相手先のホームページの管理者のメールアドレス。
内容について、問い合わせをすることができるようにこの項目をつける。
- 分類項目:登録するための分類項目、 該当する項目を1つ選択
もし、的確な項目がないときはこの項目を追加できるのでこの投稿欄の
管理者宛に、「メッセージ送信欄」を使って連絡することができる。
- 投稿者の氏名とメールアドレス:互いに誰が投稿したかを分かるようにするため、投稿の際に入力する。
- 投稿ボタン:このボタンをマウスキーでクリックすると、投稿完了。
- やり直しボタン:画面に入力したデータをやり直すときに使う。
投稿し終わった内容を取り消すには、「メッセージ送信欄」を使って連絡することが必要。
- 閲覧:登録した内容を時間列順に閲覧
主に、管理者が使う。この閲覧には、登録者の氏名とメールアドレスも表示される。
- 項目別閲覧:一般の利用者のための登録内容の閲覧画面
図2にあるように、項目別に閲覧できる。
- メッセージ送信欄:この投稿のページの管理者へのメッセージ
分類項目の追加や、登録内容の修正などのメッセージを送るためにある。
補足2. 表1の項目別の登録数の分析プログラムchk-url,add2.awkのソースリストを以下に示す。
------------------------<< chk-urlのリスト >>----------------------------------
#!/bin/csh
# urlの数を調べます。
# Coded by m-yasu, 2000-Oct-24
set f=xout
echo "### {L1,L2,,,L24}.htmlのURLの数を調べます。###"
echo "### 出力先:$f ###"
echo "### {L1,L2,,,L24}.htmlのURLの数を調べます。###">$f
date>>$f
foreach n( L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16
L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 )
set x=`cat ${n}.html|grep "URL:"|wc|awk '{print $1}'`
echo $n"/html :"$x>>$f
end
# 総数の計算
set x=`cat $f|add2.awk`
echo "総数:"$x>>$f
echo "Completed"
------------------------<< add2.awkのリスト >>-------------------------------
#! /usr/local/bin/awk -f
# calling : cat ファイル名|add2.awk
# ファイル内容のフィールドは2。数値は第2フィールド
BEGIN { x=0
FS=":" }
{ if (NF == 2) x=x+$2 }
END {print x}
|
* 宮城教育大学環境教育実践研究センター