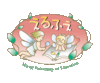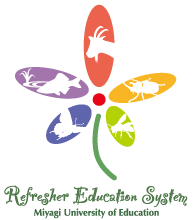2014年2月7日(金)に宮城教育大学において、「環境・防災教育セミナー 特に被災地における大学教育の環境・防災教育カリキュラムの動向」を開催いたしました。
本セミナーは宮城教育大学を含む大学教育における環境・防災教育のカリキュラムの目指すべき方向性、課題について、現状報告と情報交換を行うことを目的として開催されました。
まず、斉藤千映美教授が本学の教育復興支援センターの設立の経緯や「環境・防災教育」のシラバス等を説明した後、吉田利弘特任教授より、学校現場における防災教育の現状について報告がありました。次に、溝田浩二准教授より、実際に「環境・防災教育」においておこなっている授業について紹介がありました。
岩手大学の比屋根哲教授より、岩手大学の「地域防災研究センター」や「岩手の研究『三陸の復興を考える』」の授業について、立教大学の阿部治教授より、日本の環境教育やESDの現状について話題提供がおこなわれ、活発な意見交換がなされました。
2013年12月1日(日)にせんだいメディアテーク オープンスクエアにおいて、FEEL Sendai(杜の都の市民環境教育・学習推進会議)主催の「環境フォーラムせんだい2013」が開催され、里山の自然の貴重さと豊かさを知ってもらうことを目的とするブース「里山の自然ふたたび」の出展をおこないました。
展示内容は「自然フィールドワーク研究会YAMOI」の学生が中心となって考え、運営もおこないました。
里山をイメージする壁面ポスターを貼り、卓上では魚類の生態や動物剥製、骨のパズルを展示しました。壁面ポスターを、来場者がひとつひとつ里山の構成要素(花、魚、鳥など)を貼っていくことで、里山にどんな生きものがいるのか考えることができるようにしたり、クイズ用紙を作成し、答えを探しながらブースの全体を見てもらうように工夫しました。
動物の剥製を触ったり、魚を観察するなど子どもから大人までたくさんの人が来場してくれました。






展示内容は「自然フィールドワーク研究会YAMOI」の学生が中心となって考え、運営もおこないました。
里山をイメージする壁面ポスターを貼り、卓上では魚類の生態や動物剥製、骨のパズルを展示しました。壁面ポスターを、来場者がひとつひとつ里山の構成要素(花、魚、鳥など)を貼っていくことで、里山にどんな生きものがいるのか考えることができるようにしたり、クイズ用紙を作成し、答えを探しながらブースの全体を見てもらうように工夫しました。
動物の剥製を触ったり、魚を観察するなど子どもから大人までたくさんの人が来場してくれました。